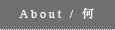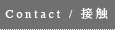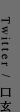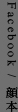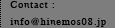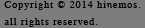|
明地 清恵・写真展 "my bedroom" 2014.9.20[土] - - 23[火] / 26[金] - - 28[日] at : hinemos -tiny wall gallery- open : 13:00 - - 20:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23日(火・祝)は明地がママをつとめる幻のバー、 "chin-wa-mario"がオープン。 Bar Open 18:00 - - 22:00 会期中の土曜、日曜は"喫茶文九"が営業します。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
主客のあわい text : 野口卓海(美術批評家 / 詩人) 私は、写真が苦手だ。特に、いわゆる「写真作品」(※1)への言葉による接近が非常に苦手だ。「写真」という言葉の指し示す対象があまりにも巨大すぎて、私自身が一貫した立場を取り続けられないためでもある(※2)。にも関わらず、今回twgのオープンに際し明地氏へ展示を依頼した理由は二つ。この場所の展開として美術や工芸だけでない多様な「ものごと」を視野に入れているため、そしてそういった今後の展開に乗じ、私自身が現代美術以外の世界の多様さについても今一度考え直したかったためである。身近な人物が撮影した写真作品はまさに、私にとって非常に大切な再入場口であったのだ。 今回展示している明地清恵の写真は、暮れゆく街並・まだ明るい夜空・向かいあう人の足・窓辺の光景といったように、被写体自体はどれも何気ないものばかりだ。明確な時間や季節が判然としない作品群は、鑑賞者に「どこかで見たような」感覚を抱かせるかもしれない。幾つかの作品に薄暮の時間帯が選択されていることも、既視感を強める要因の一つだろう。それでいながら、作品のどれもが明地自身のごく個人的な物語を想起させるに足るプライベートな親密さを持っている。この不思議な同居は、一体何に起因するのか。 当然ながら、そもそもカメラという装置は、プライベート/パブリックのあわいを解体させるような役割りを持っている。撮影者の固有で瞬間的であった視覚が、時間や場所を大きく超えた他者へ共有されるという写真の機能は、先の不思議な同居の遠因を感じさせる。しかし何よりもまず指摘しなければならないのは、その共有が撮影者自身にとっても巻き起こり続けている、という点だろう。特に、明地が行っているフィルムによる撮影→レンズ焼(※3)といった工程においては、その共有が顕著に影響する。自分自身が間違いなく過去に見ていたビジョンを、少しずつ差異を加えながら幾度も幾度も眺めなおすという行為は、撮影者である明地へどこか客観的でドライな視点を与えるに違いない。そして、その繰り返しの中で改めて見いだされる(あるいは文字通り「浮かび上がる」)モチーフや色・見せ場。幾度もの冷静な眼差しを経て、徐々に焦点を合わせられたそれらは、アナログ現像でしか捉えられない写真独自の表現足り得るのだ。だからこそ、一見何気ないような明地の写真が、じっと凝視される鑑賞にも耐える強度を持っているのだろう。 写真は、確かに科学現象だ。しかし、科学的な理を全て解しているからといって、目の前で繰り広げられる科学反応がおしなべて記号的に見えるわけではない。暗室で幾つもの去来する像と対峙する時間は、やはり神秘的で私的(※4)な体験でもあるだろう。明地の写真からは、その残り香が確かに感じ取れる。いや、それだけではない。ファインダーをのぞくこと、ピントの合っていくさま、暗室での工程、印画紙へ像が浮かび上がる様子。それら全てが、彼女にとって神秘的で私的なものなのかもしれない。さながら、ベッドルームでのやりとりのように。 |
※1:勿論、装置や文脈としての写真およびカメラを用いた「現代美術作品」ならば、批評の作法に則った接近が可能であるだろう。両者の隔たりについては、また別の機会に譲る。 ※2:何よりもまず、写真作品へは個人的な趣味判断、つまり好悪の段階が介入しすぎてしまう気がしている。常に大量の写真を見せられ続けている現代の私たちは、その好悪の判断すら無意識に近づいてしまっている。 ※3:いわゆるアナログプリントのこと。「フィルムの画像をレンズによって投影し印画紙を現像する」というこの技法は、現代では失われつつある。しかし、フィルムの像がレンズを通ってカメラ内部へと入ってきた光の作用によるものだと考えると、もう一度レンズを通して現像させるこの方法は、非常に分かりやすく理にかなっていると言える。 ※4:「私か」を「ひそか」と読む通り、「私」とは常に秘められたものなのである。 |